企業ができる残業代請求への対策について
退職した従業員から残業代不払いを訴えて、労働基準監督署や裁判所への申立てるケースが増加しています。
最近では弁護士や司法書士が残業代不払いの問題について、たくさんの人々に残業代を請求できる権利あると請求を促す広告やウェブサイトを立ち上げ、この影響から退職した従業員から残業代請求が増える可能性がでてきます。
そこで、従業員が残業代の請求をしてくる前に、事前に会社側で対策をたてておくことが重要です。無防備な状態では大変危険です。
ここからは経営者の皆様に残業代請求への対策についてお話しいたします。
まず、どの会社でも検討することができる、残業代請求への対策としては、① 定額残業代の活用
② 歩合給制度の活用
③ 業務日報の記載やタイムカードの打刻の適正化
などがあります。
1つ目の対策は、定額残業代の活用です。
これは、従業員に対し、会社が一定の残業代を毎月定額の「残業手当」として支払うことを約束する方法です。たとえば、いままで「営業手当」を支給していた従業員に対し、今後は「残業手当」を支給することに変更することにより、もしその従業員から未払い残業代を請求された時でも、「残業手当」として支払った分についてはすでに支払い済みであると主張することができます。
この場合は、雇用契約書や就業規則に「残業手当は残業代の支払いとして支給している。」ことを明確に記載することが大切です。この記載を十分にしていれば、残業手当は残業代の支払いとして認められます。
ここでポイントとなるのは、残業手当の部分を金額で特定することです。中には、雇用契約書に「月給25万円。ただし、これには30時間分の残業代を含む。」というようにしておられる会社もありますが、これはやめたほうがいいです。このような記載ではいったい基本給部分がいくらなのかが明確ではなく、万一、訴訟になった場合に裁判所が、毎月の支払に残業代が含まれていたと認めてくれないリスクが出てくるからです。
定額残業代の制度を導入する場合は、雇用契約書や就業規則への記載方法が大変重要になりますので、ぜひ咲くやこの花法律事務所にご相談ください。
次に、2つ目は、歩合給制度の活用です。
あまり知られてないことですが歩合給制度を採用することは残業代のリスクの削減になります。
多くの企業で残業代請求がされた場合にその請求額が多額になってしまうのは、会社の給与体系が歩合給ではなく時間給であるという点にあります。
たとえば、就業規則で朝9時から夜6時までが就業時間として定められている会社があったとします。休憩の1時間を除けば、就労時間は8時間です。
この会社の従業員が夜7時まで残業をした場合、時間給と歩合給ではどういう違いがでるでしょうか。
その会社の給与が時間給であれば、会社の基本給は8時間の所定労働時間分の労働に対する支払いと考えられます。ということは基本給を支払っているだけでは、夜6時から夜7時までの1時間分については全く支払いをしていないことになってしまいます。この部分については、法律上25パーセントの割増賃金の支払いが必要にありますので、結局、夜6時から夜7時までの1時間の残業について、1時間当たりの平均賃金の1.25倍の金額を支払うことになってしまいます。
これに対して、その会社の給与が歩合給であれば、会社の給与の支払いは8時間の労働の対価ではなく、実際にその従業員が労働した時間分の労働の対価です。歩合給を払っていれば、夜6時から夜7時までの1時間の残業についても、割増部分以外の基本部分は支払いをしていることになります。結果として、歩合給であれば、1時間当たりの平均賃金を計算したうえで、その0.25倍の金額を支払えば足りるのです。
もちろん、すべての会社が歩合給を採用できるわけではありませんが、このように歩合給制度を活用すれば未払い残業代のリスクを大きく削減できることになります。
最後に3つめは、業務日報の記載やタイムカードの打刻を適正化することです。
もし未払い残業代の請求が裁判となった場合に、従業員の労働時間についての重要な証拠となるのが、タイムカードや業務日報です。
ところが、現実には、従業員のタイムカードの打刻時間と実際の労働時間が一致していなかったり、業務日報に書かれている労働時間と実際の労働時間が一致していないケースが多くあります。たとえば、従業員が仕事を終えた後も、会社に残って同僚と雑談した後、タイムカードを打刻したり、業務日報に仕事が終わった時刻より遅い時刻を終業時刻として記載しているということはないでしょうか。このようなケースでもいざ残業代の請求が裁判所に持ち込まれると、裁判所はタイムカードや業務日報については実際の労働時間を示す資料として扱うことが多く、会社側で、実際に仕事をしていた時間とは違っているという主張をしてもなかなか認めてくれません。
そこで、このようなことにならないように、日ごろから会社はタイムカードの打刻や業務日報への終業時刻の記載が適切にされているかをチェックし、問題がある場合は指導していく必要があるのです。
そのほか、採用することができるケースが限定されていますが、残業代請求への対策として使える可能性のある制度がいくつかあります。ここではその中から3つご紹介いたします。
まず1つ目ですが、法律では労働時間を弾力的に運用できるように「変形労働時間制」という制度があります。
会社では、労働基準法では一日の労働時間は8時間以内、週に40時間以内と定められ、これを超える労働については残業代を支払わなければなりません。
たとえば、1年の中でも、特定の期間内だけ残業をしなければいけないという時期があり、一方で、それ以外の期間は暇であるというケースがあります。
このようなケースでも、特に対策を立てないでいると、一方でひまな期間があるのに忙しい時期だけ残業代が増えることになり、大変非効率です。
そこで、この場合、1年単位の変形労働時間制という制度の採用を検討することになります。この制度は1年を平均して1週間あたりの平均の労働時間を40時間にすればいいという制度なので、ひまな期間の労働時間を短くして、その短くした時間分を忙しい時期にもってくることによって、忙しい時期の残業代を減らすことができます。
また、特に繁忙期や閑散期がない会社でも、会社が週休2日制で祝日も休みで、年末年始、お盆を導入している会社であれば、この制度を採用して、1日あたりの所定労働時間を8時間より増やすことができます。つまり残業代が発生しにくいようにすることができます。
さらに、1ヵ月単位の変形労働時間制は、たとえば月初と月末だけ忙しいといった場合に業務量の少ない第2週と第3週の労働時間を短縮して、その短縮した分について、月初の週と月末の週に振り分けることで、月初の週と月末の週について、所定労働時間を増やすことができます。その結果、月初の週と月末の週に発生する残業代を少なくすることができます。
但し、これらの制度を利用するためには、労使協定を結び、労働基準基準監督署に届けなければいけません。また、就業規則にも変形労働時間制について書いておく必要がありますので、制度を導入するに際してはご注意下さい。
2つめに、「専門型裁量労働制」という制度があります。
この制度の対象業務は法律で定められている業務に限られています。
この制度は、従業員の仕事が専門性の高い職種である場合に、仕事の進め方や時間配分等を大幅に従業員の裁量にゆだね、その代わりに、実際に労働時間により残業代を支払うのではなく、あらかじめ定めた一定の時間を労働時間として採用するという制度です。
たとえば、ゲーム開発会社であれば「ゲーム用ソフトウェアの創作の業務」を担当する従業員に対して適用でき、広告代理店ではコピーライターの業務に従事する従業員などに適用できます。システム開発の会社であれば、いわゆるSE職には適用できますが、プログラマー職には適用できません。
適用できる職種が法律で定められているという点はありますが、大きなメリットとして、その職種の従業員については残業代を心配する必要がなくなります。
この制度の利用に関しては注意点があります。この制度を利用するためには労使協定を結んで労働基準監督署に届け出る必要がありますが、この手続きは各事業所ごとに必要です。たとえば、大阪本社と東京支店がある場合、大阪と東京の両方で届け出なければなりませんので、十分注意してください。届け出を怠っていると、いざ未払い残業代の請求を受けた時も、対応することができず、残業代を支払うことになってしまいます。
さらに、営業職のような外勤の多い職種に適用できる可能性があるのが、「事業場外労働時間制」という制度です。
これは、営業職のような外勤の多い職種については、実際の労働時間を把握しにくいことから、実際の労働時間にかかわらず、あらかじめ決めた一定の時間を労働したものとみなしてもいい制度で、就業規則に記載するだけで導入できます。
咲くやこの花法律事務所では、このような残業代のリスクを回避するために、クライアントの皆様に方法を提案しております。残業代の請求については事前の対策が重要です。まずは、お気軽にご連絡下さい。
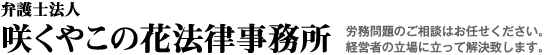

 労務問題チェックシート無料プレゼント
労務問題チェックシート無料プレゼント